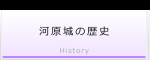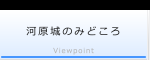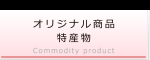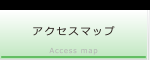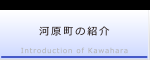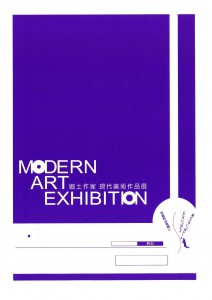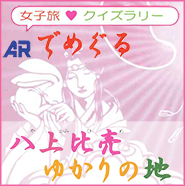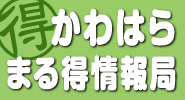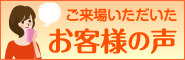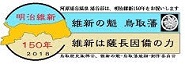ーあゆ祭り「こぼれ話」~ 子供あゆ太鼓の体験から生まれたチョットいい話ー
2013年6月14日
今年もこの季節がやってきました!子供あゆ太鼓の練習の季節が!!
毎年8月の第一土曜日に開催される「河原町 あゆ祭り」今年は8月3日(土)に35周年記念大会が盛大に開催されます。そして、町内の3つの小学校4年生が合同で「子供あゆ太鼓」を披露するのも祭りの大きな楽しみになっています。平成元年から始まった「子供あゆ太鼓」は毎年5年生から新4年生へと引き継がれて、「まるで伝統芸能みたいだ」と自分たちの太鼓に誇りを感じている子も少なくありません。その練習が毎年5月の中旬から本番前日まで続きます。
ご縁あって5年前から各学校を毎週2~3日程度 太鼓の指導で伺っています。町内の太鼓の数に限りがあるので、各学校を2~3週間づつ太鼓が移動して本番直前の3校合同練習までそれぞれ頑張っています。


先週から河原第一小学校の練習が始まりました。今週3回目の練習日は3、4時間目でしたが、練習に熱が入り時間を少しオーバーしてしまいました。給食の準備をしないといけないし、太鼓の片付けもしないといけないしで、子供たちは大急ぎで走って行きました。私は担任の先生と次の練習の打ち合わせをしていたんですが、子供たちが口々に何か叫びながら走って帰ってきました。何事かと思って話を聞いてみると、教室に帰ったらもう給食が配られていたそうです!? 誰が準備してくれたかというと5年生の子供たちだったそうです。


でも、どうして!? 話を聞いてみると、去年 自分たちが4年生の時に、練習が伸びたり疲れて遅れたりした時に、当時の5年生が給食の準備をしてくれていて すごく嬉しかったので、来年は後輩の為にお手伝いをしてあげようと思っていたんだそうです。太鼓を通して、感謝の気持ち・思いやりの気持ちが毎年しっかりと受け継がれていた河原第一小学校に真の“伝統”を感じた思いがして、私もとても嬉しく、河原の子供たちを誇りに思った出来事でした。これも、各学校の先生方のご指導や、保護者の方たちのご理解の賜物と、改めて太鼓の指導をさせていただくことに感謝する思いです。
さあ、みんな あゆ祭りのステージ目指して これからもガンバルゾー!!!
(*≧∀≦*)ノシシ (おっちー)
河原町の夏の風物詩「かわはら七夕まつり」を今年も開催します(*^_^*)
河原町内の幼稚園や小学校、福祉施設のみなさんの願いのこもった短冊が河原城を彩ります。
七夕をみんなでお祭りしましょう!

「出逢いの町・かわはら」にふさわしく、一年に一度出会う「彦星と織姫」☆彡
夜間にはライトアップされ、幻想的な”七夕ロード”がまるで天の川のよう・・・

お城とのコラボレーションも素敵です!河原の澄んだ星空のもと夕涼みするのもいいですね。
もちろん期間中お越しいただいたお客様にも短冊をご用意しております♪
大切なあの人と一緒に願い事を短冊に込めてみませんか?(*ノωノ)ポッ
~夏休みの思い出~テラコッタで作ろう!
2013年6月12日
~夏休みの思い出~テラコッタで作ろう!
日時 : 7月28日(日) 13時~15時半
場所 : 河原城 2Fイベントホール
対象 : 小学生~大人
参加費 : 500円
定員 : 10名(予約要)
人形作家の影井典子氏を講師に招き、テラコッタを使った
焼物を作ります。
器や人形、インテリア小物など色んなものを作ってみよう!
お子さんの夏休み工作のアイテムにもなりますよ!
※作品は後日お渡しいたします
たくさんのご参加お待ちしております。
(尚、定員になり次第締め切らせていただきますので、ご了承ください。)
主に河原地域で芸術活動をされている方々の力作を展示致します。
日本画・洋画・写真・陶芸・木工の多様なジャンルの作品をお楽しみください。
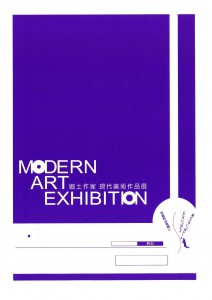



「木工アート教室」のおしらせ
☆日にち:6月16日(日)
☆時 間:13:30~15:30
☆定 員:各10名
☆対 象:小学4年生~大人
☆料 金:300円
木を使ったオリジナルジグソーパズルや車などのキットを自分達の手で組み立て、モノ作りの楽しさや難しさを体験できるイベントです。お子様の夏休みのアイテムにもなりますよ♪
ご家族で!お友達と!みんなで作って楽しみましょう!
道具や材料は準備しますので、お気軽にご参加ください。
*刃物を使いますので小学生以下の方は保護者同伴でお願いいたします。
(写真は見本です)